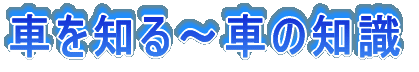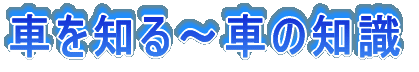| 12月25日 雪道について |
冬になると雪のあまり降らない地方に住んでいても、スキーなどのウインタースポーツや、
何かの理由で雪国に行かなくてはならない場合もある。初めて行く人や雪に慣れていない人
は不安だ。そこで、バッテリーやラジエーター液の点検など事前の準備ぐらいは誰でもする
と思うが、それでも現地に行ってからバッテリー上がりを起こしてしまう人もいる。それは
車の電装品の使い方に問題がある場合が多い。寒冷地では通常よりバッテリーの化学反応が
弱くなるためだ。特にヒーター、リヤデフォッガー、ワイパー、さらに夜間はヘッドライト
にフォグランプなど、これらの電装品は大電力を消費するので、必要最小限にとどめるべき
だ。そして他の必要のない電装品は使わないことも重要だ。車が渋滞している時などはエン
ジンが低回転で、発電量が減るので要注意だ。 |
また、以外と忘れがちなのはウインドーウォッシャー液。比較的暖かい地方から寒冷地に行
くと、ウォッシャー液がタンク内で凍結して出ないことがある。もし出たとしてもフロント
ガラスで一気に凍結して、突然前が見えなくなるというような恐怖を味わうことにもなる。
ウインドーウォッシャー液は寒冷地用と表示のあるものを、決められた濃度で使用すれば問
題はない。ワイパーブレードも、全体がゴムで覆われた寒冷地用を装着すれば万全だ。さら
に解氷スプレーを忘れずに携帯しておくと良い。これは必ず役に立つものだ。 |
チェーンとスタッドレスについて
よくチェーンとスタッドレスタイヤのどちらがいいかと聞かれるが、私は両方必要だと答え
る。私は経験上雪国では、スタッドレスタイヤだけでは走行が困難な場面に何度も遭遇して
いる。昔はスパイクタイヤを履けばほとんど大丈夫だったのだが、今のスタッドレスは凍結
路やアイスバーンなどではあまり効果が期待できない。できればスタッドレスタイヤを履い
てチェーンを携帯するのがベストだと思っている。しかし、雪国にたまにしか行かない人に
は出費がかさむので、どちらかを選ぶのだと思うが、これは雪国に行く頻度や予算、装着し
て走った時の乗り心地などで変わってくる。年に2、3回しか行かないような人はチェーンで
十分だと思う。価格も安いし、コンパクトで持ち運びに便利だ。しかし、脱着に手間がかか
り、走行時には音や振動が大きい。スタッドレスタイヤは音や振動は普通のタイヤとあまり
変わらず、安定した走行ができる。一度装着すれば雪の有無で脱着する手間もないので、雪
国に行く機会が多い人には使いやすい。
ゴム製のチェーンはかなり性能がいいらしいが、残念ながら私は使ったことが無いのでなん
とも言えないが、価格は相当高いようだ。 |
チェーン装着について
乗用車にチェーンを装着する場合は、普通はジャッキアップして行う、乗用車はタイヤハウ
ス内が狭いので作業をするのに手が入りにくいためだ。チェーンを掛けるのは左右の駆動輪
に、FRならば後輪、FFならば前輪に、4輪駆動の場合は、前輪か後輪かを取扱説明書でメー
カーから指定されている場合が多いのでそれに従う。分からない場合は前輪にかけるのが望
ましい。かけ方は、ジャッキアップして適度なスペースが確保できたら、チェーンを広げて
タイヤの上からタイヤ全体を覆い被す。下にある両端のフックを掛けてバンドでしっかりと止めて装着完了だ。タイヤハウス内のスペースが十分にあるSUVやトラックなどは、ジャッキアップしないで装着できる。ちなみに長距離トラックなどは、ダブルタイヤ用チェーンとシングルチェーンがあり、両方持って走り、状況によって使い分けている。 |